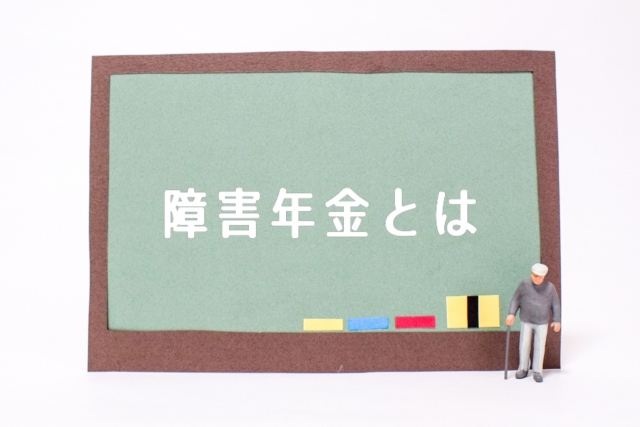障害年金とは何か
このホームページでは、障害年金についてをたくさん記載していますが、
そもそも「障害年金」とは何か?ということを本記事では書いていきます。
簡潔に言うと・・・
「障害によって、日常・労働に支障がある場合に支給される、公的年金。
”現役世代でも”もらえます」
です。でも、これだけだと
「障害」ってなに?
「日常・労働に支障」ってどの程度の支障をいうの?
どこから、いくら受け取れるの?
受け取るための手続きはどのようにするの?
こういった、疑問も生じると思います。この記事ではできるだけ簡単に概要をお伝えし、本ホームページでは、詳しくわかるように解説していくことを目指します。
公的年金って?
私たちは、加齢、障害、死亡など、さまざまな要因で、収入を得ることが困難になるリスクがあります。
こうしたリスクに対し、個人だけで備えるには限界があります。
そこで、これらに備えるための仕組みが、公的年金制度です。
公的年金制度は、あらかじめ保険料を納めることで、要件を満たしたときに
給付を受けることができる社会保険制度です。
日本の公的年金は、20歳以上60歳未満のすべての方が加入する国民年金(基礎年金)と、
会社員・公務員の方が加入する厚生年金保険があります。
そして、支給事由として、老齢・障害・遺族があります。
それに対応して、老齢年金、障害年金、遺族年金という制度があります。
障害年金の受給要件
ここで、障害年金の受給要件について見ていきます。
ざっくりいうと、
1.年金保険料の未納が少ないこと
2.初診日において、原則、公的年金制度に加入していたこと
3.障害の重さがある程度あること
以上の3つなのですが、これらざっくりなので、細かく、以下、見ていきます。
①疾病・負傷があること
当然ですが、疾病(病気)や、負傷(ケガ)があることが前提となります。以下、「疾病・負傷」を合わせて、「疾病等」といいます。
たとえば、知的障害も受給対象なのですが、知的障害を「疾病」と捉えるかは、ネットで見た限り、見解が分かれているようです。
法律上の条文だと、「疾病・負傷」ですが、「疾病・負傷・障害」というイメージで良いかと私は考えています。
障害年金の対象となる疾病は何か、というと「ほぼ全て」という答えになります。
もっとも、「ほぼ」と書いたように、一部例外があります。それは、神経症、パーソナリティ障害です。これらは、原則対象外ですが、一定の状態がある場合、対象となります。
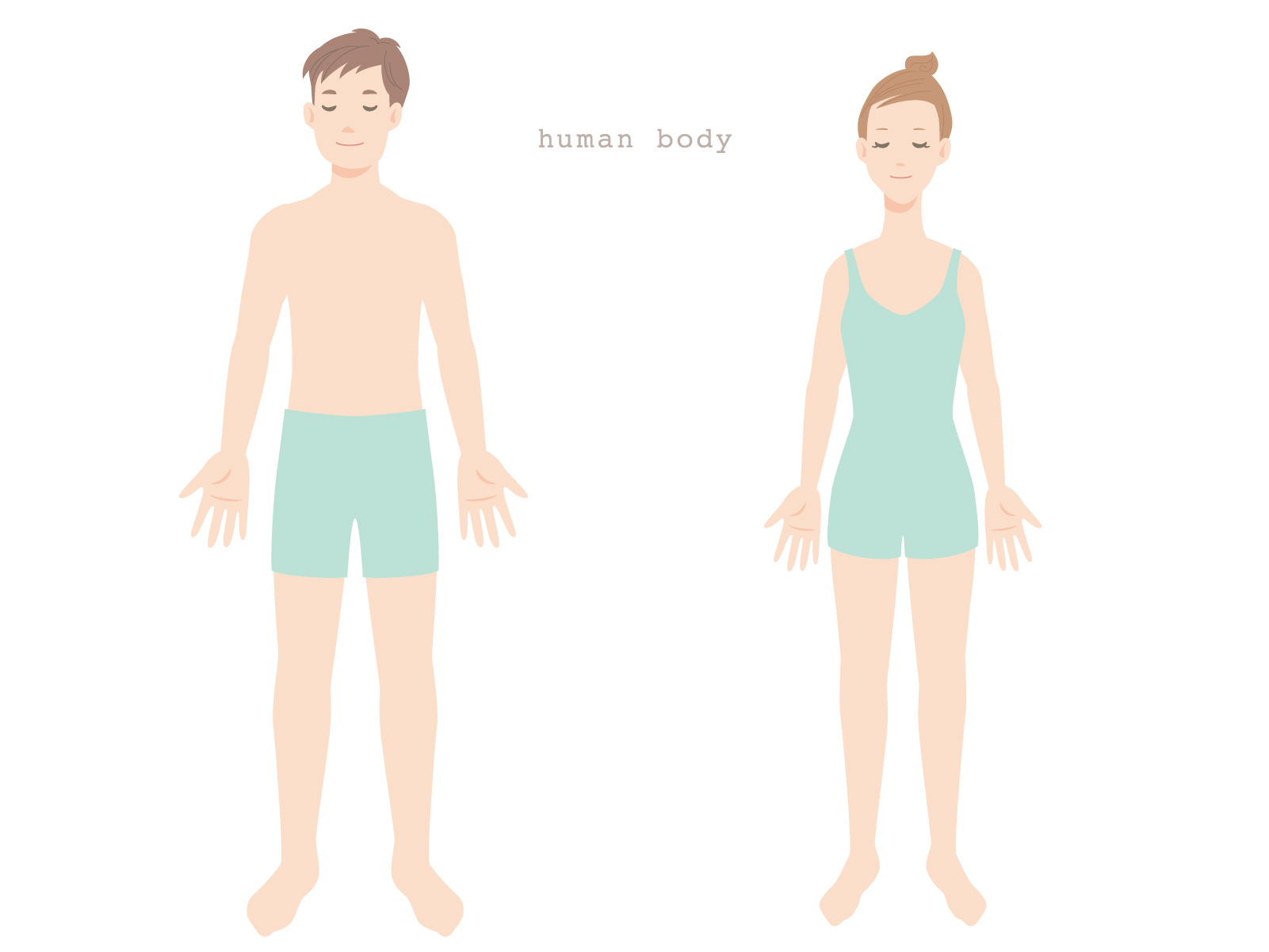
障害年金の対象となるのは、
✔ 外部障害(肢体障害、視覚障害、聴覚障害など)
✔ 内部障害(がん、糖尿病、心臓疾患、人工透析など)
✔ 精神障害(うつ病、統合失調症など)、発達障害、知的障害など
ほとんどが、対象となります
②疾病等の初診日に年金制度に加入していること
「初診日」が果たしてどういった意味なのかは、とても重要です。別の記事で記載する予定です。
この「初診日」において、年金制度(上記の、「国民年金」「厚生年金」)に加入していることが要件となります。
もっとも以下の例外があります。
初診日において、
・20歳未満
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満(老齢基礎年金繰上受給をしている場合を除く)
これらの場合は、「初診日において年金制度に加入の有無」については、不問となります。
③初診日前に、一定の年金保険料を納めていること
初診日の前においても、年金保険料が未納だらけだと、年金を受け取ることができません。これは公的年金が、保険制度であることからこのような要件が課されています。
もっとも、初診日が20歳前である場合は、そもそも原則20歳前は年金制度に加入しないことにより、この要件は不要になります。
④初診日から一定程度経過していること
疾病になったからすぐに障害年金をもらえるのでありません。「初診日」から原則、1年6ヶ月たたないと年金がもらえません。
例外として、1年6ヶ月より前の障害が固定した場合は、1年6ヶ月より前にもらうことができます。
⑤一定程度の障害の状態であること
一定の障害重さであることが、年金受給要件となります。この一定の重さについても、今後解説してきます。
⑥年金を請求すること
障害年金は、上記1から5の要件を満たしていたとしても、役所に対して、請求(申請)をしないと年金を受け取ることができません。
また、一定の場合、65歳までに請求することが要件になります。これについても、今後解説していきます。
まとめ
このように①から⑥までの要件がありますが、一般的には、②の加入要件、③の納付要件、⑤の障害の程度要件の3つの要件が説明されることが多いです。
年金受給額
では、障害年金はいくら受け取れるでしょう?
障害の重さや、初診日に加入していた制度によって、また、配偶者・お子様の有無によって、各人受け取れる年金額は異なります。
障害の重さによって受け取れる年金額が変わります
まず、障害が重い方から、1級、2級、3級、障害手当金となります。重ければ重いほど、受け取れる年金額が大きくなります。
初診日に加入していた制度が何かによって、受け取れる年金額が変わります
「初診日」に厚生年金(共済組合も含みます)に加入していた場合は、障害厚生年金が支給されます。
1,2,3級とありますが、3級より軽く、一定の要件を満たす場合は障害手当金がもらえます。
そして、1,2級の場合は、2階建て部分の障害厚生年金に加え、、1階建て部分として障害基礎年金がもらえます。
「初診日に厚生年金に加入していた人」以外が支給されるのは、障害基礎年金の1階建て部分だけであり、障害厚生年金や障害手当金は支給されません。
そのため、「初診日」にどの制度に加入してたかが、年金受給額をきめるため、とても重要になるのです。
ご家族の状況によって、年金額が変わります
障害厚生年金1,2級の場合で、配偶者(これも一定の要件があります)がいる場合は、配偶者の加算がつきます。
障害基礎年金で、18歳年度末(障害あるお子様の場合20歳まで)のお子様がいる場合は、子の数に応じた加算がつきます。
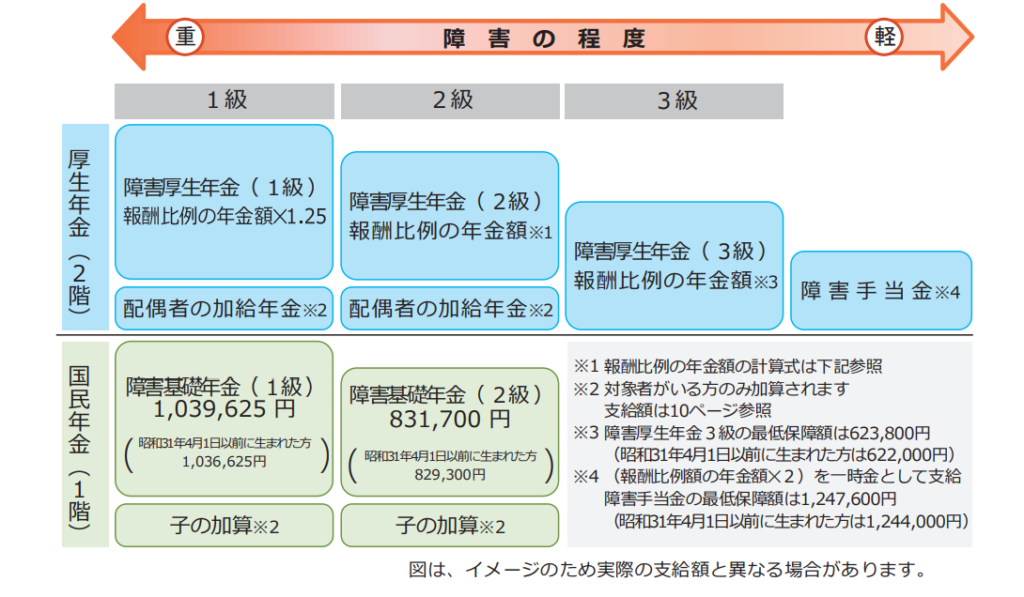
表は、日本年金機構作成 障害年金ガイド令和7年版より引用
さいごに
なんとなく、障害年金制度のイメージはつきましたでしょうか?
本ホームページでは、基本的なことから応用編まで、随時記事をアップしていく予定です。